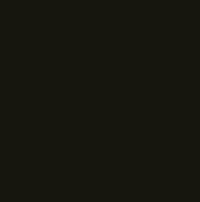2010年01月18日09:15

日本の伝統色とはその色も名も趣があるのは、自然から見つけられた色を取り
入れたものだから、その名からもさまざまな事を推測できるのです。
今朝は宍色(ししいろ)です。
宍(しし)とは肉を指す言葉だそうで、文字通り肉色ということになる。思いだして
「ししおき」を調べてみると「肉おき」とあり、肉のつくさまを表している。
宍(しし)=肉(しし)であるからピンク色をこう呼んでいます。
日本人は魚食が長く、明治になって肉鍋やすき焼きなどを食べ始めたと聞いて
おりますが、実際には野山の獣を獲っては食べていた。
民話の世界などでは、鳥や兎、狸にキツネまでが食べられる話が多く出てまい
ります。
肉食をよしとしません風潮があっただけのようであります。
また宍色とは日本人の肌の色を象徴したと言われております。
連日ながら絵の具のお話、小学生の頃の絵の具には「肌色」という色があり、
図画の時間にスケッチした友達の顔などはこの色で塗っていた。
簡便であり、そのものでありました。
20歳の頃、思い立ちまして油絵を習うことにいたしまして画家についてみた。
デッサンの間はさほど腕の違いはないのだと言われておりましたが、これに
絵の具を置く時から違いが生まれます。
人の顔にはさまざまな光があたり、影やその命や表情などが現れている。
画家の絵の具は顔に赤や青や黒まで置かれてゆく。
どうしてもそんな風に絵の具を使えない者は「漫画」などと言われてしまいま
した。
表面を見て内面を描くこと、その命のさまを顔に見ること、「肌色」に塗った
顔に画家は容赦なく青の絵の具を置いて修正するのです。
あるお金持ちのお嬢さん大学生に絵の勉強の為にフランスに行きたいのと
相談され、「行くべきだよ」と背中を押した日がありました。
彼女はしばらくして教室には来なくなった。
顔に赤や青を置くことができた彼女はいったいその後どんな人生を歩んだか。
そんなことを思い出しています。
宍色ししいろ≫
カテゴリー │色字典

日本の伝統色とはその色も名も趣があるのは、自然から見つけられた色を取り
入れたものだから、その名からもさまざまな事を推測できるのです。
今朝は宍色(ししいろ)です。
宍(しし)とは肉を指す言葉だそうで、文字通り肉色ということになる。思いだして
「ししおき」を調べてみると「肉おき」とあり、肉のつくさまを表している。
宍(しし)=肉(しし)であるからピンク色をこう呼んでいます。
日本人は魚食が長く、明治になって肉鍋やすき焼きなどを食べ始めたと聞いて
おりますが、実際には野山の獣を獲っては食べていた。
民話の世界などでは、鳥や兎、狸にキツネまでが食べられる話が多く出てまい
ります。
肉食をよしとしません風潮があっただけのようであります。
また宍色とは日本人の肌の色を象徴したと言われております。
連日ながら絵の具のお話、小学生の頃の絵の具には「肌色」という色があり、
図画の時間にスケッチした友達の顔などはこの色で塗っていた。
簡便であり、そのものでありました。
20歳の頃、思い立ちまして油絵を習うことにいたしまして画家についてみた。
デッサンの間はさほど腕の違いはないのだと言われておりましたが、これに
絵の具を置く時から違いが生まれます。
人の顔にはさまざまな光があたり、影やその命や表情などが現れている。
画家の絵の具は顔に赤や青や黒まで置かれてゆく。
どうしてもそんな風に絵の具を使えない者は「漫画」などと言われてしまいま
した。
表面を見て内面を描くこと、その命のさまを顔に見ること、「肌色」に塗った
顔に画家は容赦なく青の絵の具を置いて修正するのです。
あるお金持ちのお嬢さん大学生に絵の勉強の為にフランスに行きたいのと
相談され、「行くべきだよ」と背中を押した日がありました。
彼女はしばらくして教室には来なくなった。
顔に赤や青を置くことができた彼女はいったいその後どんな人生を歩んだか。
そんなことを思い出しています。